No.39(2021年)
病気不安症に対する森田療法:コロナ禍の病気不安症
伊藤 克人(東急病院心療内科医・東急電鉄株式会社統括産業医)
はじめに

「自分は病気ではないか」と不安になることは、だれでも経験することです。そのようなときに、どのように行動するかは、人それぞれ異なります。
病院を受診する人もいれば、とりあえず放っておいて日常生活を続ける人もいます。
しかし、そうやっているうちに、いつの間にか忘れてしまうということもみられます。
一方、一旦不安になるとそれが徐々に心の中を占めていくようになり、日常生活が二の次になるような場合には、「病気不安症」といって病気そのものよりも、それに伴う不安が問題になります。
また、2019年から始まった新型コロナウイルス感染症の流行により、それに関係した「病気不安症」もみられるようになりました。

■森田正馬(もりた・しょうま 1874〜1938)
医学博士、慈恵医大精神科・初代教授。 若き日に、みずから不安症(神経症)に悩んだ。その結果、のちに1920年ごろ、画期的な精神療法「森田療法」を創始する。いまでは日本森田療法学会があり、「森田療法」は世界的に知られている。
(1)本質は「ヒポコンドリー性基調」
森田療法の適応になる人には、「神経質素質」という性格素質がみられます。このような神経質素質の特徴のひとつとしてヒポコンドリー性基調というものがあります。
これは、ひと言で言えば心気的な傾向が強いということで、身体の些細な不調を重大な病気と勘違いして不安になることをいいます。
しかし単なる勘違いだけではなく、それに伴う行動が日常生活に影響していきます。ここでは1〜3の事例を挙げて説明していきます。
【事例1・Aさん 36歳会社員 男性】

朝起きると頭痛がしました。会社へ休むことを連絡して、病院を受診しました。 検査の結果、異常はありませんでした。医師からは「心配ありません」と鎮痛薬が出されました。薬を飲めば軽くなるのですが、思うようには治らないため、別の病院を受診しました。
会社で仕事をしていても、頭痛のことが気になってはかどりません。重要な仕事があるのですが、なにか重大な病気があるのでは、とそのことばかり考えてしまいます。
【事例2・Bさん 46歳主婦 女性】
健康診断で乳がんがみつかり手術を受けました。その後、ホルモン治療を続けていますが、再発を心配する毎日を過ごしています。
一方で、旅行へ行ったりコンサートへ出かけたりなど、これまでの楽しみは続けていました。しかし心には常に再発の不安があり、以前のようには楽しめません。
そのうちに家事をするのも億劫になり、外出する気持ちにもならず、家にいて悶々(もんもん)とするような生活が続いています。
【事例3・Cさん 22歳大学生 男性】
コロナ禍の折、オンラインの授業が多く、外出をすることも少なくなりました。そしてテレビやネットからの情報を見ているうちに、さらに外出を制限する気持ちが強まりました。
しかし、大学の図書館で資料探しをしなければならず、久しぶりに電車に乗りましたが、中にはくしゃみをする乗客もいて、感染に対する恐怖が強くなります。
そのうちに、たまに行われる対面授業の出席もできなくなり、今度は授業の単位が取れるかどうかが心配になってきました。
1〜3の事例では、それぞれにヒポコンドリー性基調がみられます。つまり、病気に対する不安がみられますが、その悩み方はさまざまです。 しかし、それにより、普段のその人らしい日常生活が損なわれています。
(2)「事実唯真」が通じなくなる
病気不安症の治療としてよくみられるのは、次のような説得療法です。
- 「Aさんの症状について、いろいろな検査をした結果、異常がみられません。病気ではないので心配ありません」
- 「Bさんにはがんが再発したような結果はどこにもみられません。今の治療を安心して受けていれば大丈夫です」
- 「感染するといっても、実際の患者は人口の1%にも届きません。外出したからといっても、そうは感染しないものです。Cさん、安心してください」
森田療法では「事実唯真」という言葉で、事実は事実として動かせない、事実の前では平伏(ひれふ)すしかない、というように事実をしっかり受け止めることの大切さを表しています。しかし、病気不安症では病気や症状の実態を事実として受け止められず、不安や恐怖が膨らみます。そのような心の状態がみられるときに、「心配ない」という説得をしても、
- 「なにかの病気にかかっているはずだ」
- 「再発の危険はなくならない」
- 「気づかずに感染するかもしれない」
・・・という心の構えを崩すことは困難なことです。

また、一旦は「そう説明されたのだから、それを信じるべきだ」「不安や恐怖を感じるのがおかしい、感じるべきではない」と受け止めても、実際には不安感情を持ったままなのです。
そのため、思想の矛盾【注1】が働いて、逆に不安感情にとらわれ、さらに増幅されていくという精神交互作用【注2】により、心の悪循環の渦に巻きこまれてしまうのです。
森田博士は、このようなときに、ヒポコンドリー性から生じる予期の心配、恐怖、不安の感情が発生しやすいという「感情的基礎」があって、病気や症状の実態を事実としてみないで、誤った捉え方をすることが二次的に生じて、病気不安症が発症する、と考えました。
したがって、このような感情的基礎に着目しないで、いたずらに病気や症状が心配ないものと説得することは、病的な心理を患者と共同で深めることになります。そして、[恐怖心の火に薪(まき)を加えて、ますますその感情を養成するような結果となる]といいます。
また、[患者は自分の病気に関する恐怖心を根絶して完全に安心の心持ちになろうと努力するものだが、そうすればするほどますます意のままにならないで、いよいよ失望、悲観におちいる結果となる]といいます。
(森田正馬著『神経質の本態と療法』白楊社より)
一方、このような「感情的基礎」がみられない場合でも、病気や症状があれば、それに対する不安や恐怖は当然の感情としてみられます。
しかし、それ以上でもそれ以下でもないため、病気や症状の実態を事実として説明されると、不安や恐怖がそれ以上に発展することはありません。
【注1】
神経質者にみられる「かくあるべし」という理想と、現実の自分との矛盾(ギャップ)。
【注2】
ある感覚に対して過度に注意が集中するとその感覚はより一層鋭敏になる。さらに、その感覚が固着され、注意と感覚が相互に影響しあって益々その感覚が拡大される精神過程。
この日記のやりとりから伝わるのは、患者の、不安があってもそれを問題としなくなった態度、そして現在の境遇に従っていこうとする確かな決意です。
森田療法ではこの境地へ導くためにどのようなことを指導するのでしょうか。次の章では、この森田の評をもう少し深く読み込み、森田療法の治療の目標と治療内容について述べたいと思います。
(3)治療としては心の流動性の回復が大切
さて、病気不安症では、説得よりも感情的基礎に焦点を当てた治療が必要になります。 患者は、ヒポコンドリー性基調という特性から、心は不安や恐怖の方向を向いて立ち止まり、それがまたその感情を増幅させるという悪循環がみられます。
普段、心はいろいろに動いているものです。日常生活では朝食を食べる、出勤の準備をする、家を出て駅へ向かう、会社へ着いたら机に向かう、仕事で会議に出るなど、いろいろなシーンに応じて心は動いていきます。
子どもが熱を出したとしても、仕事中に一瞬思い出して心配はするものの、すぐに「仕事の心」になっています。心の流動性が回復することは、不安や恐怖という感情に執着して立ち止まった心にとって、とても大切なことです。それでは、心の流動性の回復を促すためには、どのようにしたらよいのでしょうか。
私が実際の臨床で行っているのは、「もしも今の悩みがなければ、どんなことをしたいのですか」という問いかけです。
患者は、この病気を治したい、症状をなくしたいという欲望が、自分のためのより建設的な生の欲望【注3】の実現に繋がっていることに気づかないことがあります。病気や症状に対する不安や恐怖と格闘している間は、その先にある自分らしい生き方の方向が見えなくなっているのです。そこで、さきほどのような問いかけをすることにより、患者本来の生の欲望へと目を向けてもらいます。
- 「仕事に集中して、いま以上に成果をあげたい」
- 「今まで楽しんでいた旅行やコンサートへ行ってみたい」
- 「自由に友人と話をしたり、部活で体を動かしたりしたい」
というように、患者の本来の生の欲望(本心)が透けて見え出します。しかし、ここでヒポコンドリー性基調のみられる感情的基礎が立ちはだかるのです。
- 「でも、この症状があって動けません」
- 「やはり再発の心配がなくならなければスッキリした気分になれません」
- 「それでも感染の不安をなくして行動するのは無理です」

このように、患者には完全主義的な傾向がみられます。症状がなくならなければ何もできない、不安が気になってどうにも動けない、など、完全に安心できないことを理由にして、「……したい」気持ちを遮ります。その結果、心はそこに留まったまま動きません。
そこで私が患者に問いかけるのは、「症状をなくしたい気持ちだけを大切にして、いま、……したい気持ちをのけ者にしたら、とても不自然な生き方になりませんか」ということです。そして、「症状をなくしたい気持ちはそのままにして、いま、……したい気持ちを、やってみる方へ動かしてみましょう」と続けます。
- 「頭痛が気になるのはわかりますが、気になりながらでも仕事に気持ちを向けて、まずはやってみることです。心がそこで動き始めると少し弾みがついて、さらに先へ、というようになります」
- 「再発の不安はよく理解できますが、不安を抱えていては何もできないというわけではありません。不安を感じながらでも、……したいという自分の気持ちを大切にして、実際に無理のない範囲でやってみるようにしましょう」
- 「感染に対する不安は、だれでも持っています。しかしせっかくの大学生活を不安の色一色で染めてしまうこともないでしょう。オンラインで友人と会話するなどの工夫をして、……したい気持ちを少しずつ実現してみましょう」
このようにして、基礎的感情によって留まっている心を、そこから動けるように援助していきます。
【注3】
人間の絶えず向上・発展しようと志向する欲望。人間本来の建設的なエネルギー。
(4)心が動くきっかけは「純な心」
森田博士は、はっと思ったら、さっと手を出す、というように、その時の感性でとらえた「純な心」で素直に動くことが大切である、といいます。自分の自然な感性を大事にすることは「今の自分のままでよい」という自己肯定感を高め、自分を肯定することに繋がります。
逆に「やろうと思ったけれど、そんなことをしてもムダだ」「行こうと思ったけれど、何のタメにもならない」と自分の感性を否定してしまうのは、「今の自分のままではダメだ」ということを自分に刷り込むことになります。
「症状がなければどんなことをしたいのですか」という問いかけで、患者の心の方向を日常生活に向けて、さらに「症状があっても……したいと思ったら、実際にやってみましょう」と、「純な心」で行動を起こすことを促します。
晴れていて散歩に出ようと思ったら散歩に出てみる、キュウリが美味しそうなので食べてみたいと思ったらレジへ持っていく、庭に雑草が生えていて綺麗にしたいと思ったら雑草取りをしてみる、といった日常の小さなことに対して働いた、自分自身の感性を大切にします。
そうすることによって、「今の自分のまま、やっていればよいのだ」という気持ちが定着していきます。
そしてひとつひとつの小さな行動につられて、心の流動性が回復していきます。
(5)心を占めていた不安や恐怖が少しずつ勢力を失う
心の流動性が回復して日常生活を送れるようになると、病気や症状に対する不安や恐怖で占められていた心に、少しずつ隙間ができて、そこに自分らしい楽しみや満足、希望や期待といったものが入り込みます。そして、不安や恐怖が占めていた部分がさらに小さくなっていきます。
【事例1・Aさん 36歳会社員 男性】
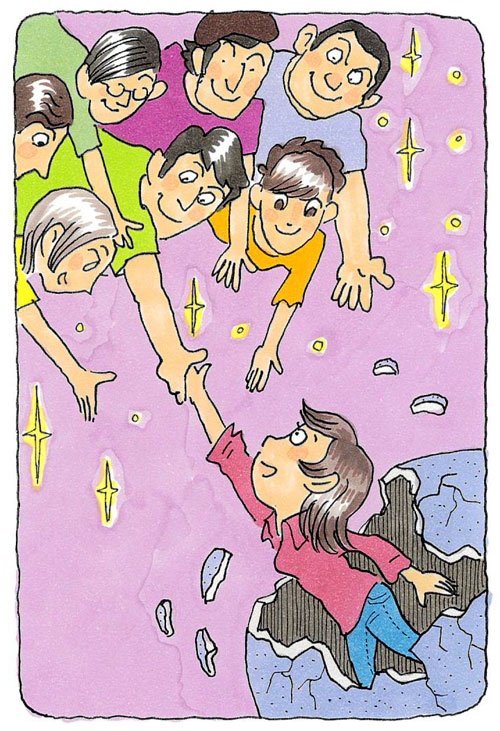
頭痛はあるものの、仕方なく、いま、目の前に抱えている重要な仕事をやっているうちに、仕事の成果が少しずつ見えてきました。
そして、夢中になってやっているときは、頭痛がほとんど気にならないので不思議です。
頭痛が完全になくなったわけではないので、重大な病気にかかっているかもしれないという不安が完全になくなったわけではありません。
しかし、医師が言うように、ひとまず様子を見る気持ちになって、毎日を送っています。
【事例2・Bさん 46歳主婦 女性】
乳がんの再発の不安は常にあります。しかし、いま、生きている自分として、不安を感じている自分のままでよい、を出発点としてやれることもいろいろあるのだと気づきました。
海外旅行は無理でも、国内旅行やいろいろなコンサートに行くようになりました。そのようなときは、以前の自分を取り戻したかのような満足感を味わうことができます。
【事例3・Cさん 22歳大学生 男性】
コロナ禍はいつまで続くかわかりません。しかし、感染の不安を抱えながらも対面授業や図書館へ行くことが増えるにつれて、少しずつ、こうやれば感染は防げるのではないか、と思えるようになりました。
家でじっとしていて、テレビやネットの情報を長時間みながら感染の不安を感じているほうが、かえって不安を大きくしてしまいます。
授業中や図書館で調べ物をしているときに、ふと気がつくと不安はほとんどありません。
もちろんマスクの常時着用、手指の消毒、手指で顔を触らない、マスクを外して食事をするときは会話をしない、などの基本的な注意はしっかり守っています。
おわりに
病気不安症におちいると心の流動性が失われてしまう、ということは多くの人が経験していることです。「純な心」で自分の感性を大切にしながら動いてみれば、少しずつ心の流動性が回復していきます。一方、周りに病気不安症の人がみられたら「病気はそんなに心配するものではない」と説得するのではなく、その人とともにこれまでの生活をふりかえり、やりたいと思ってやってきたことの中から、その人本来の生の欲望を見出すようにします。そして、そのような建設的な生の欲望(本心)に心を向けて、普段の生活の中でその発揮を促すように支援することが大切です。
PDFファイルをダウンロード

